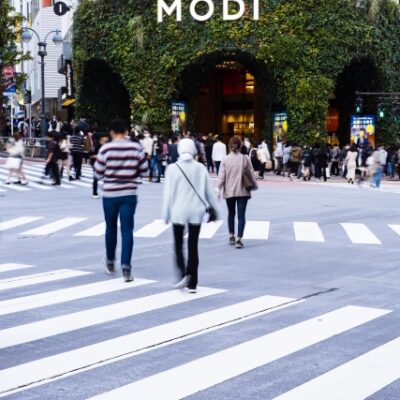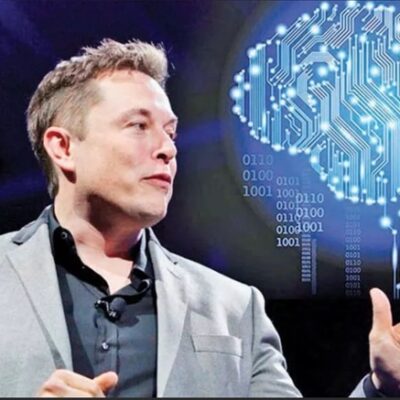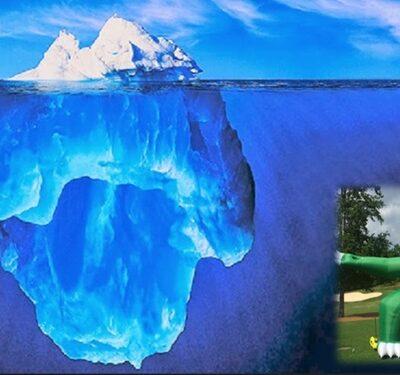今日は雑誌【古武道】の中で面白い言葉を見つけました。
【かたち】のない形をもつ! 大切さ
たしかに・・・打撃でも
(かたち)フォームが崩れれば、成績が崩れる。
しかし自分の【かたち】があれば、すぐさま修正して
勝負が楽しめる。
生活のかたち(習慣)が崩れれば、体調や感性も鈍る。
○基本の型から始まり~無形の【かたち】にいたる=を持つ。
これは大切なことだと
僕は親友の父親が、武道場をひらいていたことから、20代の頃は
野球のオフシーズンなど、中国武道を親しんでいました。
今も肩を抜く、膝を抜く、丹田の強化などは
ソフトボールや野球に応用しています。
しかしこれも、真剣勝負の試合がないと忘れてしまっているんですね。。
呼吸法や、西行水、正中心などもしかり
だから、無精で負けず嫌いな私は、20代の頃は
親睦会のソフトボールや野球がとても苦手だったんですね、
、
照れちゃって、真剣になれないから
どうゆう顔をしてプレーすればいいのかわからないだから、若いころは
必至になって職場を盛り上げて、親睦会のスタッフを率先して活動はしたものの
その親睦会のソフトボールが原因で、
スランプになった事もあるくらい・・・(笑)。
逆に、強弱のある事象や相手にも、
変幻自在な【かたち】のない形を持ている状態であれば、
これも【かたち】をもっていなかったのが原因。
おのずから(反射的に)自然に対応出来ているのですね。
簡単なようでなかなか・・・奥が深い。
師匠の言葉を思いだします。
「真髄なんてものは聞いてしまえば簡単な事、
ただ
言葉で知っているのと、出来るのとでは、
天地のひらきがあるもの・・・」
なんだとか
あの人、西田俊之にそっくりだったなー。